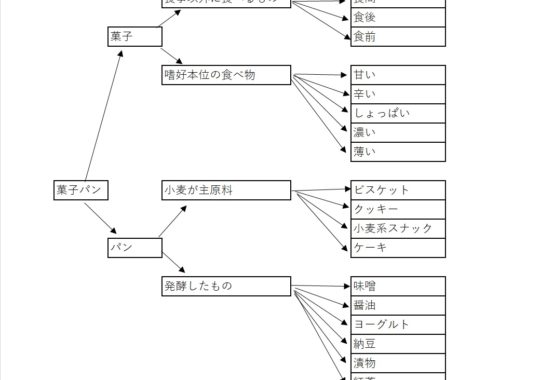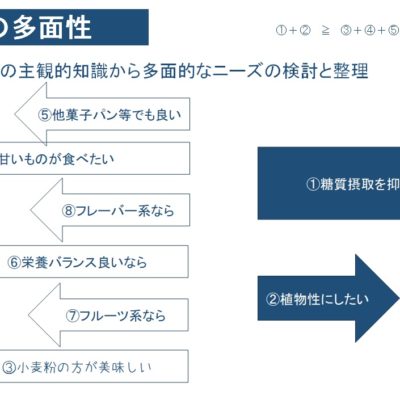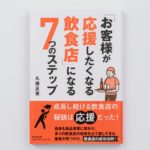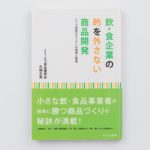今回は冷凍食品を製造販売する手順や背景について、簡易に整理しました。
1.冷凍食品を製造するには
単刀直入に言いますと、冷凍食品は、以下の2つの設備があれば実現できます。
⇒急速冷凍庫(リキッドフリーザー)
⇒真空包装機
急速冷凍庫については、種々のメーカーのものがありますが、1番のおススメは液体急速冷凍庫です。
例えば、こちらのサイトのものです。

おススメの理由は、食するときの「圧倒的な食味」です。マイナス18℃へ冷凍が実現するまでのスピードが圧倒的に早く、食材の細胞の損傷が少なく、風味が劣化しないからです。
2.冷凍食品の主たる加工工程(工程毎の要件確認)
・冷凍前処理
これは、食べられないものを取り除き、食べれる部分のみにすることを言います。魚なら腸(はらわた)を取り除いておく、野菜なら、根を取っておくといったことです。さらに、調理しやすいよう味付けをしておいたり、解凍し温めたのち、すぐに食べれるようにしておくなどを指します。
・急速冷凍
冷凍前処理をしたものを、冷凍するとき、一般的な冷蔵庫等で冷凍すると、野菜や魚の細胞が損傷し、結合水が流出してしまいます。そうなると、風味や品質の劣化になってしまうものです。そこで、急速冷凍という手法を使い、一気に温度を下げ、短時間で冷凍する「特殊な冷凍能力」を持った冷凍庫が必要になります。
・包装の適切性
出荷後から消費者に届き、適切な管理下のもとで、風味や品質の劣化に至らない包装形態を模索します。一般的には、真空包装機を使い、中身の酸化を抑えるようにします。
・マイナス18℃以下で保管
生産から販売(お客様の手元に届く)まで、一貫してマイナス18℃以下を保てるように管理しなければなりません。従って、そのような管理設備を持っていない小売店に卸すことは原則、タブーです。飲食店等が物販強化の一貫で取り組む場合は、店内にマイナス18℃以下で保管できるようにします。
3.許認可の確認
冷凍食品を製造するには、以下の確認を忘れないようにしましょう。
・品質表示
表示は食品表示法で定められています。表示に必要な項目は下記になります。ただし、JAS法によって定められた食品(餃子、春巻き、フライ)には個別に品質表示基準が定められています。
⇒冷凍食品である旨
⇒名称
⇒原材料名
⇒添加物
⇒内容量
⇒期限表示(賞味期限、消費期限)
⇒保存の方法
⇒冷凍前の加熱の有無
⇒食する際の加熱の必要の有無
⇒製造者名または加工者名
⇒製造所または加工場の住所
⇒栄養成分表示
・営業許可
営業許可取得に必要な条件は以下になります。
⇒人的要件
⇒設備要件(共通基準・特定基準)
ここについては、最寄りの保健所に相談すると話が早いです。
久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。
講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。
2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。
近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。
主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。