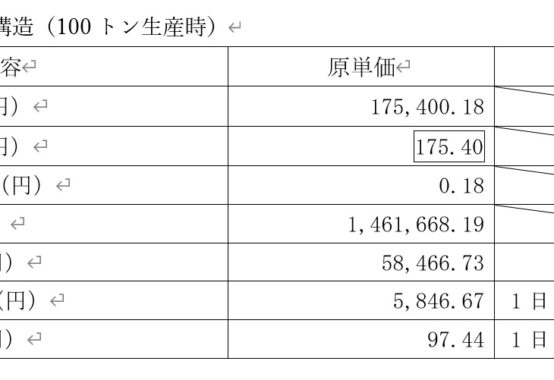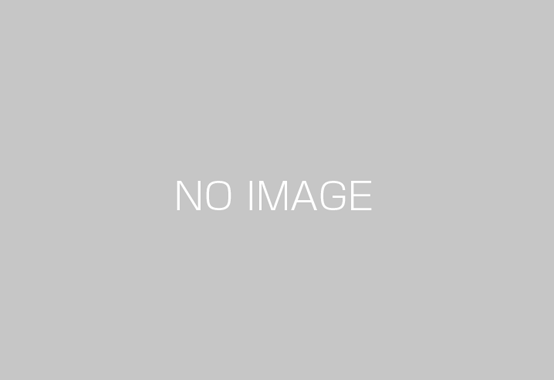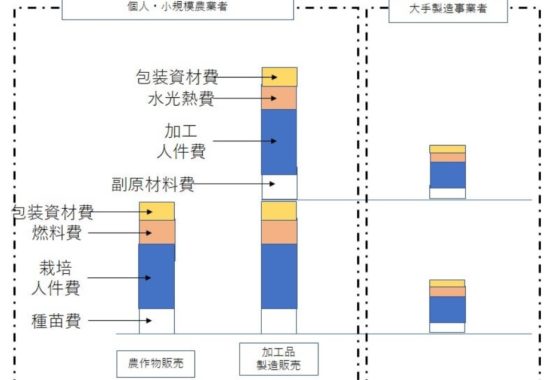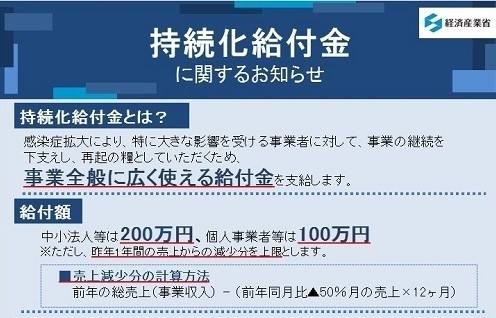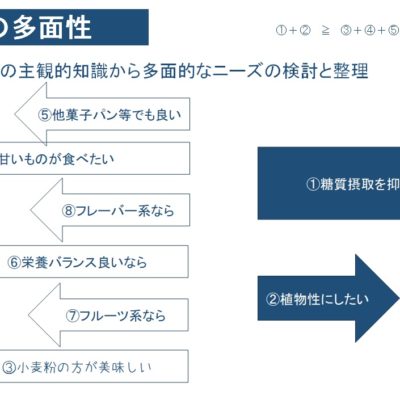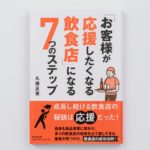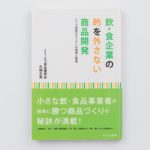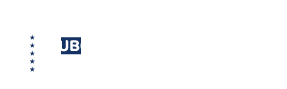皆さんの事業の周りには、
種々の2次データが存在しますね。
この2次データは、経営や運営において、種々参考にできるわけですが、
私が1番オススメしたい活用方法は「適切なターゲットの設定」に役立てることです。
ポイントは因果関係がありそうな2次データに視点を合わせること。
例えば、学習塾が以下のような2次データに注目したとしましょう。

これは、テレビの視聴時間と子供の学力の関係性の2次データです。
テレビ視聴時間が長いほど、学力が落ち、テレビ視聴時間が短いほど学力があがっているデータです。
このグラフは傾きが直線ですので、因果関係がありそうですが、果たして、どうでしょうか。
子どもが自ら、テレビ視聴時間を全て管理できるとは思えませんし。親や保護者の存在が背後にありそうですね。
親や保護者が「勉強しなさい!」とテレビを見ている子供達に教育するから、視聴時間が減り、学力があがるのでしょう。このように2次データの背後には、その結果(ここではテレビ視聴時間と学力)に影響する要因が存在することがあります。つまり、これを交絡因子と言います。
つまり、テレビ視聴時間が短い⇒学力あがる
これがこのグラフの真意ではなく、テレビ視聴時間が長い⇒親や保護者が教育⇒テレビ視聴時間が短い⇒学力があがる これが真意だと言えそうです。
このように一見、因果関係に見える2次データを探し出し、その背後に交絡因子(ここでは、親や保護者の存在)があるようであれば、そこがターゲットにすべき相手!ということです。
学習塾は、例えば小学生の子供に直接営業するわけにはいきません。無論、親や保護者に営業するでしょう。これが当然なのは、交絡因子から説明できるのです。
さて、みなさんの商売、適切なターゲットを設定できていますか。ぜひ、周りの2次データに着眼し、ご自身のターゲットを探してみてくださいね。
事例 佃煮

上記に説明ありますが、佃煮の需要が伸びるのは、御米の新米の時期に・・
そうであれば、ごはんの御供に。これが提案すべきターゲット像なのでしょう。
久保 正英(中小企業診断士・マーケティングコンサルタント)

加工食品事業者や飲食店等の消費者向け商売の「マーケティング」戦略立案と実行支援に日々取り組む。 支援する事業者のスキルや、置かれている事業環境を踏まえた「実現性の高い」支援が好評である。
講演やセミナー、執筆においては、「出来ることから出来るだけ実行」をモットーに、実効性の高い内容を傾聴、傾読できる。
2016年には、記号消費論を活用した「集客の手法論」を広く世間に公開し、その内容が認められ「中小企業庁長官賞」を受賞した。
近年は、存在価値論を支援研究テーマに掲げる一方、農林水産省や環境省の委員を2013年以降現在まで歴任しており、飲食業、食品製造業、農業、水産業といった業種の政策への提言も積極的に行っている。
主な著書に『飲・食企業の的を外さない商品開発~ニーズ発掘のモノサシは環境と健康(カナリア書房)』 『「お客様が応援したくなる飲食店」になる7つのステップ (DO BOOKS・同文館出版)』がある。